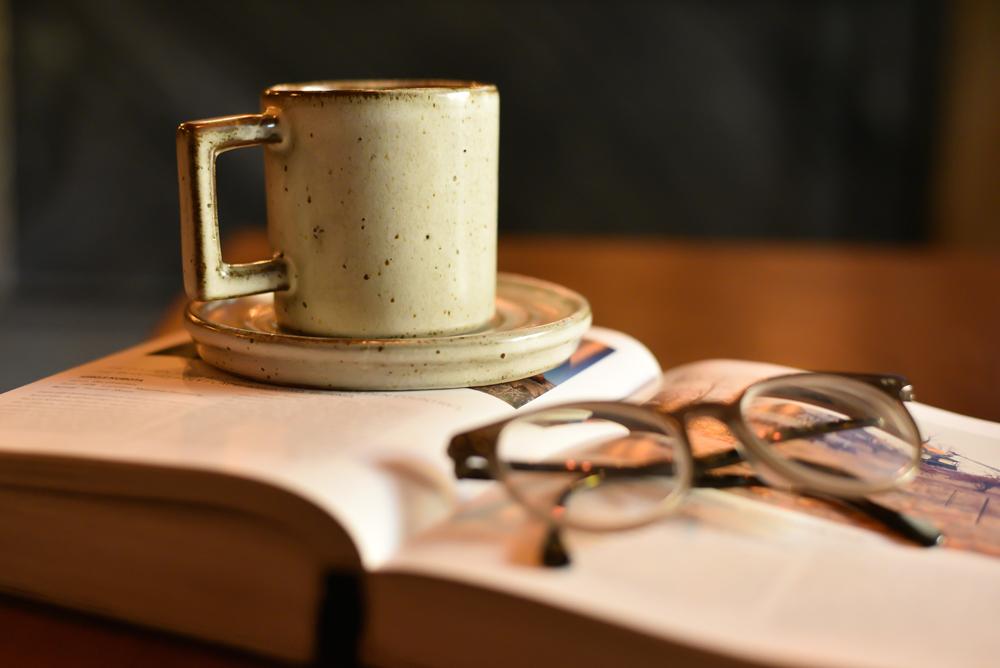-
コラム 賢人の思考 ~コロナ禍の自粛生活で考えたこと、その1~
2021.06.01
八星篤先生に「ワクチン接種について」コラムを書いていただきました。
コラムの中で、鹿児島県十島村のワクチン接種について取り上げておられますが、この対応事例は企業経営でも活かせるのではないでしょうか。
事前の計画・準備とコミュニケーションは企業経営で必要不可欠なものですが、加えて「動画」による情報共有は新たな手法だと思いました。
当社でもこれから技術継承や理念継承、教育などで動画を活用してみたいと思います。
○著者プロフィール
つくだ社会科学研究所
代表 八星 篤(はちぼし あつし)氏

1972年 東京大学経済学部卒業
1972年 第一勧業銀行入行
1996年 広報部長
1997年 企画室長
1998年 横浜支店長
2000年 執行役員調査室長 兼 第一勧銀総合研究所専務取締役
2002年 みずほ銀行執行役員調査部長 兼 みずほ総合研究所専務取締役
同年 みずほ銀行退職
2003年 株式会社サカタのタネ監査役(社外)就任
2008年 株式会社サカタのタネ取締役(社外)就任
2013年 株式会社サカタのタネ取締役辞任
現在、危機管理、経済・金融等の講演・研修活動に従事 。なお、八星氏は高杉良著「金融腐食列島」シリーズの登場人物のモデルの一人と言われている(八星氏が第一勧業銀行総会屋事件時の広報部長時代がモデル)。
○テーマ
「コロナ禍の自粛生活で考えたこと、その1」
「ワクチン接種について」
講演・研修活動も無くなり、友人との会合も次々に中止になった高齢者である私にとって、コロナ感染防止の観点からの「必要緊急の外出」とは何だろうかと考えてみました。
持病の薬をもらいに医者に行く、生活するために必要な買い物に行く以外は、必ずしも「必要・緊急」とは言えないのです。高齢者はコロナに感染すれば重症化するリスクが高いと言われ、重症化するととても苦しいと何度も繰り返し言われると、いきおい、家にいて、テレビを見たり、本を読んだりする時間が長くなりました。余生が長いとは言えないのに、友人・知人とも会えず、無為な時間を過ごさせられていると思うことも多かったです。しかし、久しぶりに昼間から、ワイドショーを始めTVの番組をじっくりと見る機会がありました。
ワイドショーではコロナ関連と東京オリパラ関連のニュースが大部分でしたが、同じようなニュースを見ていても
①ワクチン接種の順番についてそもそも何故こうなっているのか、その理屈を考えてみることや素晴らしい事例に出会って感激したこと
②以前に先輩に教えてもらった事柄だがそれの具体的な事例と思うこと
③東京オリパラについて思うこと
④リスク管理やコーポレートガバナンスの上で考えておかなければならないこと等々
そう思って見ていると、今まで自分が考えてみなかったことや見過ごしてきたことの中にも、いろいろなヒントがあるということを発見しました。
今回は①についてお話します。
なぜ、ワクチン接種は高齢者が優先なのでしょうか。先に述べたように、高齢者はコロナに感染すれば重症化するリスクが高いというのがその理由でしょう。しかしこれだけでは十分とは言えません。一般的に高齢者は体力・免疫力が低下していることから、他の病気であっても重症化するリスクは高いのではないかと思います。一方で高齢者は、仕事や学業のために外出をせざるを得ない方々に比べれば、自粛がやりやすいので (働いておられる方や介護施設等に入居されている方は別ですが)、ワクチン接種は、むしろ自粛が仕事上等で難しい人を優先した方が良いのではないかと私は考えていました。ただ、もし高齢者を優先する理由があるとすれば、今回のコロナウィルスについては、重症化した場合に、他の病気に比べて医療に掛かる負担が極めて大きい、コロナを含めたすべての病気の重症者に対する医療崩壊を防ぐためには、ワクチン接種は高齢者優先とする必要があるということでしょう。従って、コロナウィルスのさらなる変異や今後発生するかもしれない新たな感染症の場合、常に高齢者優先ではないということも理解しておく必要があると思います。
ともあれ、現在の政府の方針が高齢者優先である以上、自分の思いはさておき、接種予約券が到着した以上は、なるべく早く自分の接種を済ませて、次の順番の方が接種を受けられるようにしようと思います。ワクチン接種を巡っては、様々な議論がされていますが、日本のワクチン接種率が欧米主要国と比べると、現状かなり低水準にあり、それが国の政策の結果ということは、事実でしょう。この理由としては、そもそも日本独自のワクチンの開発体制が不十分であった、罹患率が低い水準にあったので、その段階で日本がワクチンを大量購入することは世界の批判を受ける恐れがあった(東京オリパラの開催は大量購入の理由にはならなかったのかとの疑問がありますが)、厚生労働省の体制整備が遅かった、医師会の協力体制が弱かったなどの指摘が続いています。これらは、ワクチン接種にテーマを絞って議論し、論点を整理して、今後に生かしていくことが必要と思います。
私が地方自治体のワクチン接種の取り組みの中で最も素晴らしいと思ったのは、NHKのTVで見た鹿児島県十島村でのワクチン接種です。これは、単にワクチンのスムーズな接種に留まらず、より広い範囲での行政や民間のリスク管理の在り方やコミュニケーションの円滑化などに関する好事例と思いますので、ご覧になった方もいらっしゃるかと思いますが、ご紹介します。
十島村には、120キロにわたって連なる7つの有人離島がありますが、医師が常駐していないことから、鹿児島県の医師や看護師が協力して村営のフェリーの冷凍庫でワクチンを保管しながら、7つの島を巡り、2日間で400人以上のワクチンをリレーのように接種していくという難事業に成功したのです。医師・看護師・村の職員たちは、予定通りに接種を終えられるのか緊張感が漂っていたそうです。それも当然、フェリーは物資や住民を運ぶ重要な交通手段ですから、ワクチン接種のための特別便とはいえ、通常の運航スケジュールに影響を及ぼさないためにも、大幅な日程変更は不可能だったのです。ひとつの島に滞在できる時間は平均で2時間足らず。決められた時刻までに必ず奄美大島の名瀬港へ到着しなければならないという厳しい条件でスタートしました。さらに、接種後の副反応や悪天候など、アクシデントが起きるとすべての日程に影響が出る懸念もありました。いわば一発勝負ともいえるワクチン接種を成功に導いたのは、事前の綿密な準備でした。村は、ひとつの島をモデルに、住民の協力を得て、一連の接種にどれだけの時間がかかるかを実験しました。接種会場のレイアウトは、7つの島でほぼ同じ。会場ではテントを活用して問診、接種、休憩が行われていましたが、それぞれの島で、会場は当然変わるのですが、どこの島でもチームが同じように動けるようにするための工夫でした。さらに、その様子を動画で撮影し、それを、それぞれの島に常駐する看護師に送ったそうです。実際の接種チームと一緒に作業できるのは、当日の限られた時間のみ。接種作業のイメージを事前に共有するため動画を活用し、それぞれの島では、何度も事前の訓練を行ったそうです。
関係者の円滑なコミュニケーションを、動画を利用して実現することに成功し、実際にTVを見ていても、非常にスムーズな動きで、手際良く接種が行われていきました。今では各地の自治体でそれぞれの状況に応じた対策が行われているようですが、この仕組みや動画の活用を、4月という先例のない時期に考え出したことはすごいことだと思いました。
さらに、接種予定者の中には当日体調不良の人が出るなどで、ワクチンが余ることも予想されていました。一度解凍したワクチンは使い切らなければ無駄になってしまいますが、計画を指揮する保健師の方は、ワクチンが余った場合には、誰に接種するかも事前に決めていました。余ったワクチンは、接種チームを島まで乗せてきたフェリーの船員たちに接種することになっていました。船員は島の生活物資を運搬する重要な航路を支えていることに加えて、もし島で感染者が発生した場合、搬送に関わる可能性もあります。実際に、当日体調不良等でワクチン接種の難しい人が出たので、予定通り船員に接種を行いました。接種を受けた船員は、「ワクチン接種をして、安心して島の人たちを運ぶことができるので良かった」と話していました。TVでは紹介されませんでしたが、悪天候の場合、想定以上に時間のかかった場合等あらゆる事態に備えて、計画が立てられていたことと想像します。幸い天候にも恵まれ、無事に7つの島をつないだ1回目のワクチンリレーが終了しました。決め手は非常に細かい部分まで責任者の保健師が計画を立て、その情報を島の診療所看護師にしっかり伝えた。そこには住民の安心した生活を守りたいという思いとチャンスはたぶん1回限りという危機感があったと思います。
十島村の2回目のワクチン接種では、1回目以上に厳しいと言われる副反応への対応が心配されていました。万が一、医師たちが島を離れたあとに島民の体調が悪くなった場合は、ドクターヘリや自衛隊ヘリで搬送しなければならないそうです。幸いにも5月25日から2回目の接種が行われ、26日までに希望しない人や体調不良の人を除いて、高齢者以外も含めた対象の住民すべてが2回の接種を終えたそうです。接種を終えたのは、対象となる16歳以上のすべての住民のうち、およそ9割にあたる476人。鹿児島県内では高齢者への優先接種が進んでいますが、高齢者以外も含めた対象の住民が2回の接種を終えたのは十島村が初めてです。島民のお一人は「島に医師がいないという危機感がある中、希望する対象住民に2回の接種が終わったのはありがたく、ほっとしています。ただ、子どもがいて、変異株の流行は怖いので気を緩めず、今後も対策を徹底していきたいです」と話していました。
ワクチン接種を巡っては、ワクチンが余った場合の対応が不透明であったり、医療関係者の名のもとに、余り関連が無いと思われる方の接種が行われたり、東京の大規模接種会場で接種を受けた人が、地方自治体の予約を取り消さなかったりする事例が問題視されています。事前の準備の不足、コミュニケーションの不足、危機感の欠如がその根底にあると思います。これは、ワクチン接種のみではなく、日常の様々な事例に当てはまることだと感じています。

タケシタの公式Facebookにいいね!する
このカテゴリーの他の記事
カテゴリー一覧
タケシタのサービスについての創意工夫や仕組みについて説明します。
-
民泊関連
-
賢人の思考
さまざまな専門家の方々に、「賢人の思考」と題しコラムを寄稿いただきます。
-
社長の頭の中
noteでも記事を連載中です。ぜひ合わせてご覧ください。
-
タケシタをサポートする専門家
弁護士・行政書士をはじめとする各種専門家にサポートして頂き、より良いサービスを提供できる体制を整えてまいります。
-
広報部リポート
竹下産業の広報部からのレポートです!
オフィスの情報媒体処理は、
タケシタにお任せください
- 竹下産業株式会社 〒123-0852 東京都足立区関原1-14-2
-
03-3887-1761 営業時間/9:00~17:00
- 一般廃棄物収集運搬業
- 474号(東京都23区)
- 産業廃棄物収集運搬業
-
016684号
東京都(保管積替含む) 千葉県 神奈川県 埼玉県 茨城県 栃木県 群馬県 山梨県 福島県 長野県 静岡県 愛知県 大阪府
- 特別管理産業廃棄物収集運搬業
-
016684号
東京都 千葉県 神奈川県 埼玉県 茨城県 栃木県 群馬県 山梨県 福島県 長野県
- 産業廃棄物処分業
- 016684号(東京都23区)
- 古物商
- 306681102711号(東京都公安委員会)
※「T-CUBE」は竹下産業株式会社の商標登録です